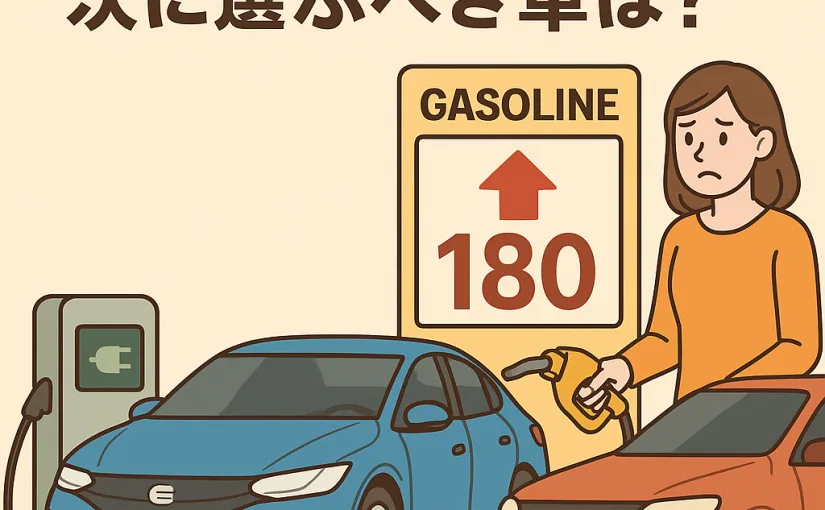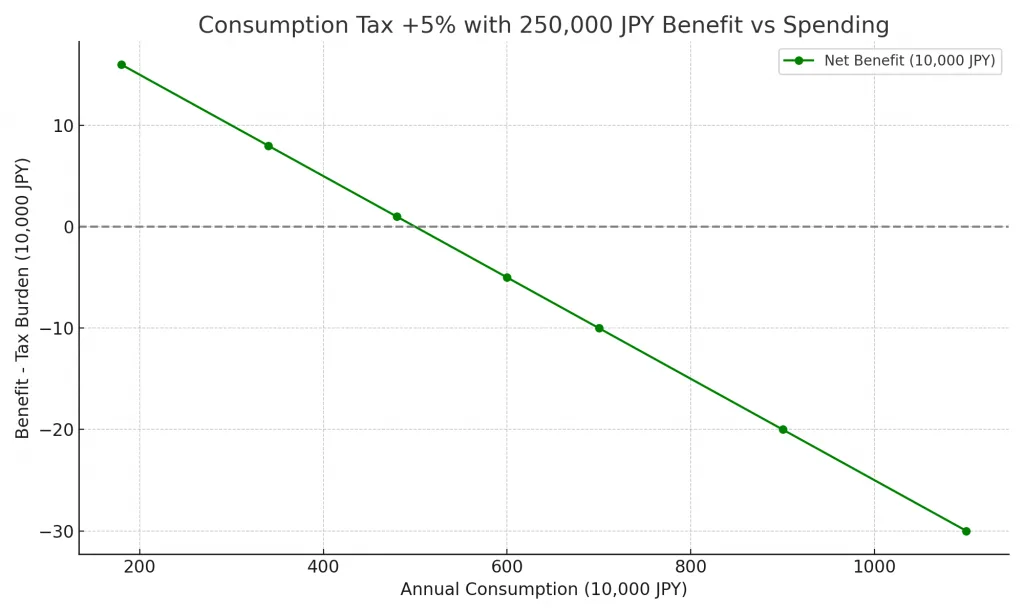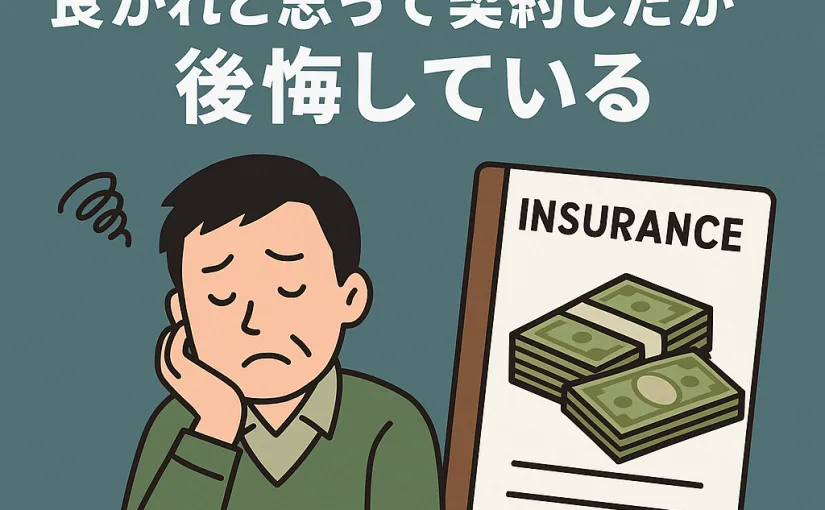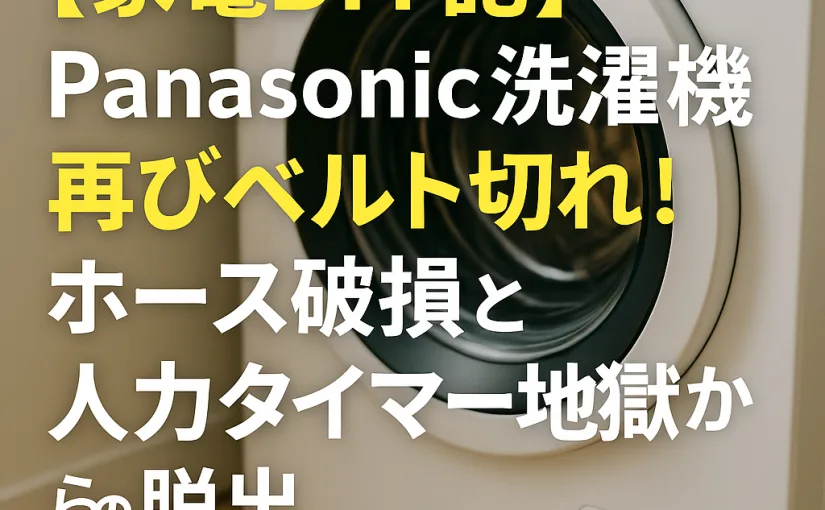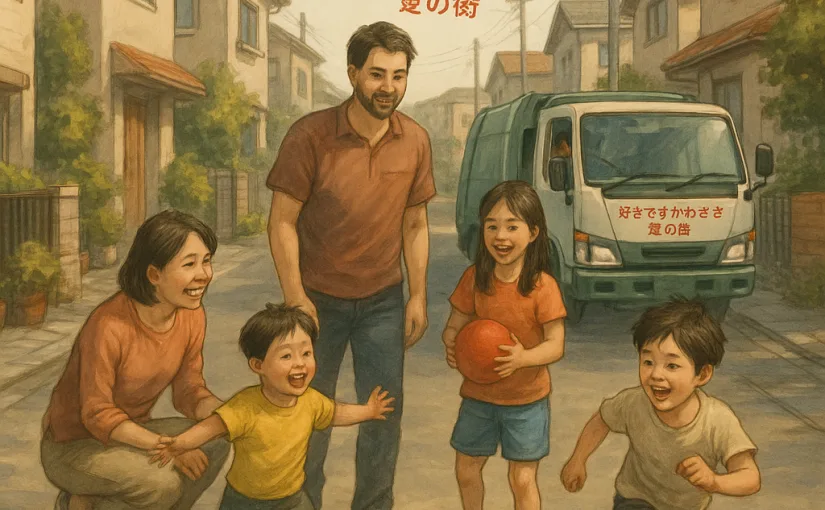「またガソリン代、上がってる…」
そんな声が、最近コンビニの駐車場や職場の雑談で増えてきました。
2025年春。
日本全国のレギュラーガソリン平均価格は180円前後。満タン1回で1万円近く飛ぶことも珍しくなくなってきました。
家計は苦しい。でも車は手放せない。
そんな状況の中、「電気自動車(EV)にすれば安くなる?」という疑問がわいてくるのは自然なことです。
でも、EVは本当に経済的?
まだ高いんじゃないの?
バッテリーって10年後どうなるの?
この記事では、そういった不安をひとつずつ整理しながら、
**「次の車選びで失敗しないための考え方」**をお伝えします。
EVって本当に“安い”の?エネルギー効率で見ると…
「発電に化石燃料を使っているなら、EVもガソリン車も結局同じじゃないの?」
実は、それでも**電気自動車のほうが“圧倒的に効率がいい”**のです。
ざっくり言うと:
- ガソリン車は、エンジンの中で燃やしたエネルギーの約20%しか動力に使えていない。残りの80%は熱などで無駄になります。
- 一方EVは、火力発電・送電・充電というプロセスを経ても、60〜70%の効率で車を動かせる。
つまり、発電段階から含めてもEVは2〜3倍効率的なんです。
特に都市部のように“ストップ&ゴー”の多い運転では、エンジン車はブレーキでエネルギーを捨ててしまいますが、EVはそのエネルギーを回収して再利用できます(回生ブレーキ)。
実際のコストで比べたら、どっちが安いの?
仮に年間1万km乗るとした場合のランニングコストを比較してみましょう。
● 電気自動車(例:テスラ モデル3)
- 自宅での夜間充電なら、1kmあたり約5円
- 年間5万円
- メンテナンスはほぼ不要(オイル・ベルト不要)
- 税金も優遇あり(自治体によって補助金あり)
● ガソリン車(1.5Lクラス)
- ガソリン180円/L、15km/Lなら1kmあたり約12円
- 年間12万円
- オイル交換やエンジン部品の消耗もあり
- 税金は通常通り
→ 年間で約7万円、10年で70万円の差が出ます。
初期費用こそEVはまだ高めですが(例:モデル3で500〜600万円)、日々の維持費でじわじわと元が取れる構造になっています。
EVにも弱点はある。でも使い方次第で“最強の選択肢”に
もちろん、EVにもデメリットはあります。
- 航続距離:500km前後が主流。遠出には不安
- 充電時間:急速でも30分~1時間かかる
- インフラ:特に地方では充電器が少ない
- バッテリー:10年超で劣化する可能性も
とはいえ、「毎日の通勤や買い物」だけなら全く問題なし。
自宅で充電できる環境さえあれば、**毎晩スマホを充電するような感覚で“燃料満タン”**にできるのです。
しばらくは「街乗り=EV、長距離=エンジン」の時代
今の時点での最適解はこれです:
| 用途 | ベストな動力 |
|---|---|
| 毎日の街乗り | 電気自動車(EV) |
| 高速移動・旅行 | ハイブリッド or ガソリン車 |
| 過疎地・山道 | ガソリン(インフラ未整備) |
| 商用トラック | 今はディーゼル、将来は水素やEV |
つまり、1台で全部をカバーする時代から、使い分けの時代へ。
トヨタやホンダが「EV・HEV・FCVすべてを同時に進めている」のも、この変化を見越してのことです。
そして5年後、10年後にはどうなる?
では、今ガソリン車に乗っている人が、今後どう備えるべきか?
未来を見据えてポイントをまとめておきます。
■ 5年後(2030年ごろ)
- EVの車種が今よりさらに安価&多様に
- 街中での充電器が大幅に普及
- ガソリン車の下取り価格が少しずつ下落
→ 次の買い替えではEVを候補に入れるのが現実的
■ 10年後(2035年ごろ)
- 欧州などでガソリン車の「新車販売禁止」がスタート
- 日本でもEVシフトが本格化
- バッテリー技術の向上で航続距離1000km超えの車も登場予定
→ ガソリン車を買う理由は“趣味”だけになる時代へ
結論:次に選ぶ車で、家計と時代対応の両方が変わる
EVはまだ「全員にベストな選択肢」ではありません。
でも、**「使い方が合う人」にはすでに“圧倒的にお得な選択肢”**になっています。
- 近距離がメインの人
- 自宅に駐車スペースと充電設備がある人
- 子どもの送迎や通勤で毎日乗る人
こうした人にとって、EVは「高い買い物」ではなく「将来の家計防衛策」です。
そして今後、EVがさらに安く、速く、便利になっていくのは確実。
5年後、10年後に困らないためにも、今のうちにEVという選択肢を“知っておく”こと自体が資産になる時代が来ています。