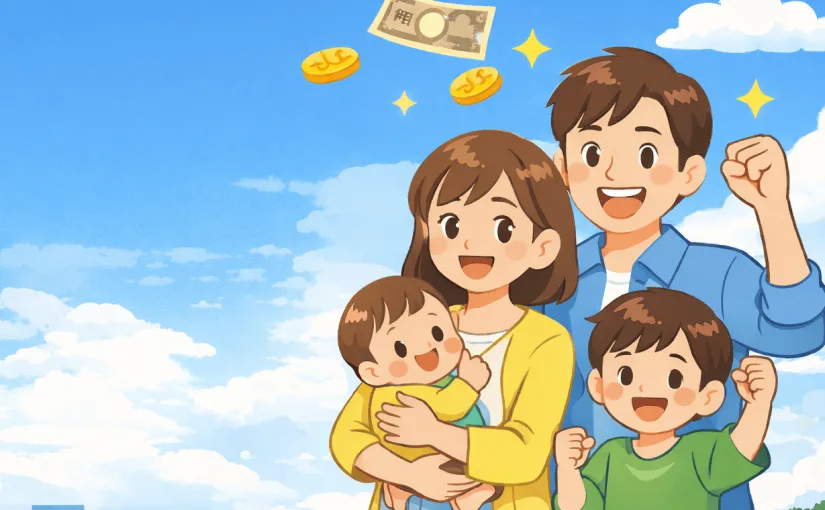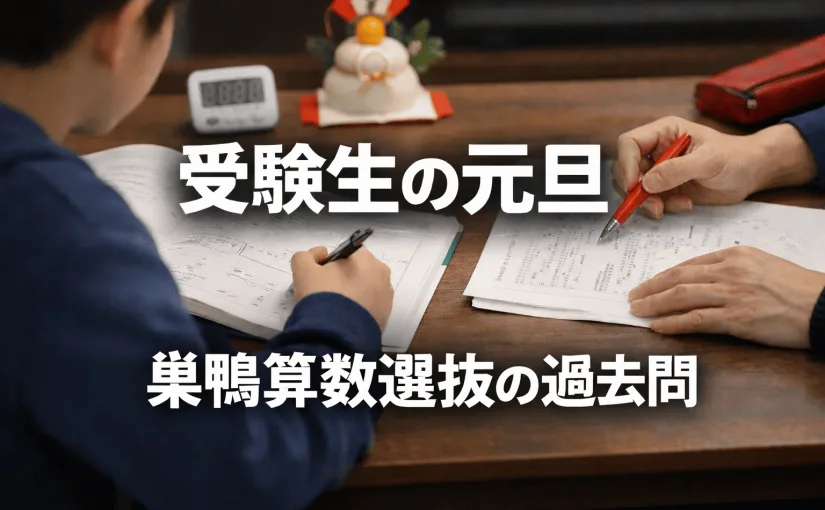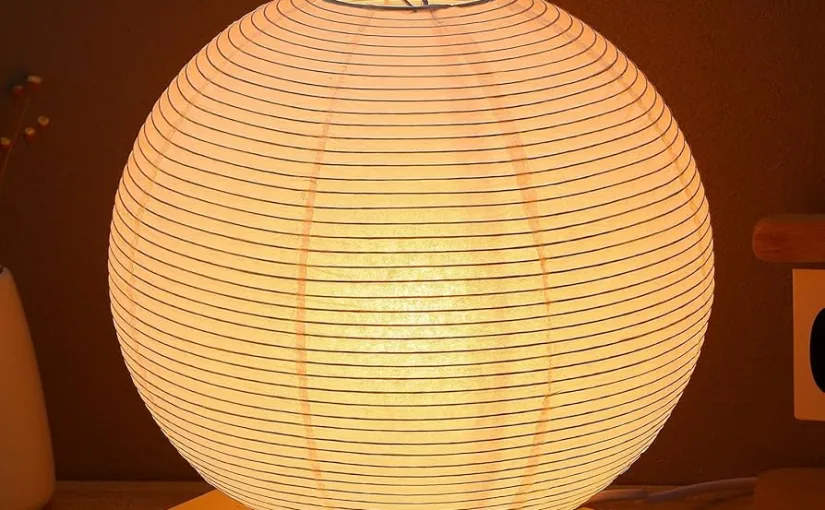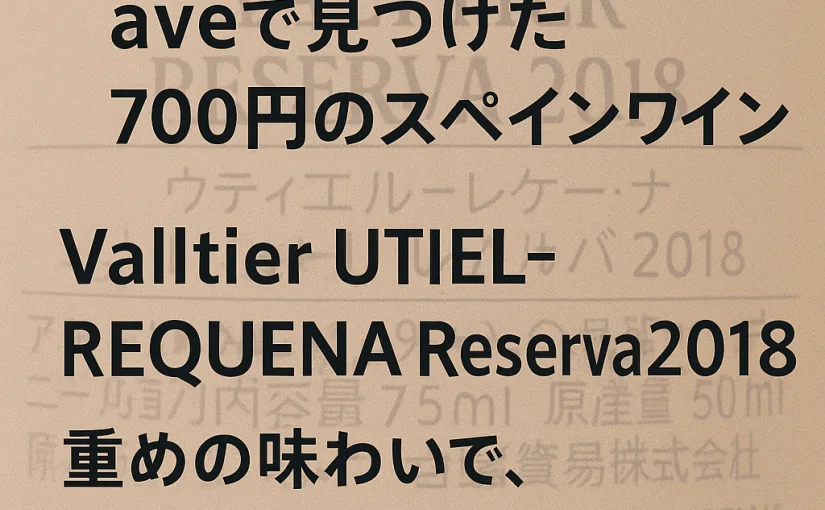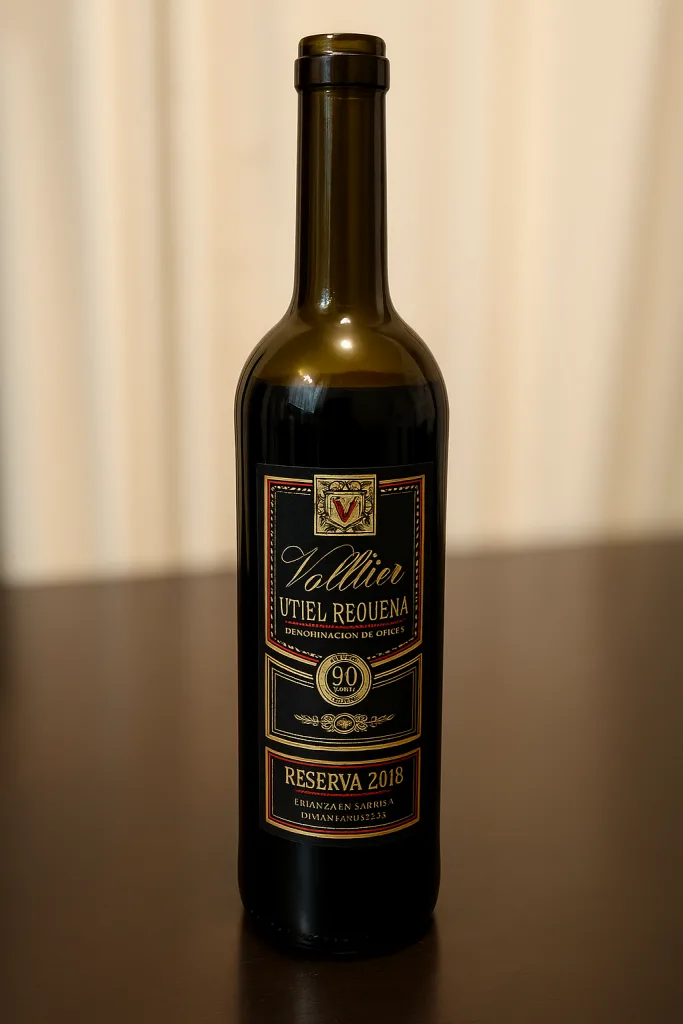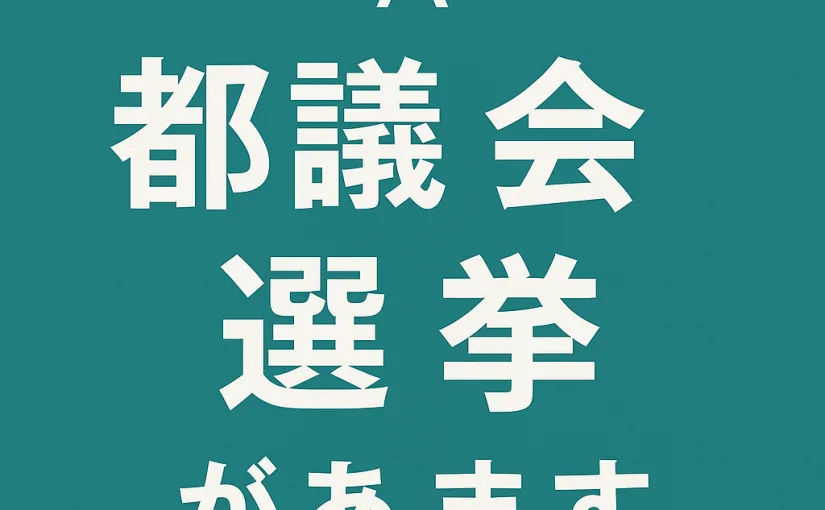もうすぐ東京都議会議員選挙が始まる。告示は6月13日、投票日は6月22日だ。
僕は川崎市民なので、北多摩第四選挙区で投票することはできない。でも、それでも、どうしても応援したい人がいる。
それが「再生の道」を掲げる 仲れいこさん だ。
僕は再生の道という新しい挑戦が、東京の政治をもっと面白くしてくれると信じている。
だけど、正直に言うと、この戦いは甘くない。
現実は厳しい。勝つためには「応援してるよ!」と気楽に構えているだけじゃだめで、データとロジックに基づいた、狙いと戦略が必要だ。
だから、この記事では僕なりに、**「仲れいこさんが当選するために必要なこと」**をまとめてみたい。
北多摩第四選挙区の現実:仲れいこさんは「泡沫候補」に見えるのか?
まず、選挙ドットコムで北多摩第四選挙区の候補者を見てほしい。
- 渋谷のぶゆき(自民党・現職・56歳)
- 原のり子(共産党・現職・59歳)
- 細谷しょうこ(国民民主党・元職・71歳)
- 仲れいこ(再生の道・新人・36歳)
…どう見ても、仲さんだけがダントツに若い。
そして正直、選挙ドットコムの掲載順やプロフィールの見え方を見ても、**「泡沫候補感」**が漂ってしまっているのが現状だ。
なぜそう見えてしまうのか?
- 再生の道はまだ無所属のような新しい政治団体で、組織票が弱い。
- 他の候補は現職や元職で、知名度や支援組織がしっかりしている。
- 仲さん自身も新人で、まだ有権者への浸透が浅い。
このままだと、**「負けそうな人に票を入れてもムダ」**という空気に飲み込まれてしまう危険性が高い。
だからこそ、仲さんの強みを前面に押し出す戦略が必要だ。
仲れいこさんの「能力」は確かなものだ
仲さんには明確なアピールポイントがある。
それが、学び直しの経験と、実際にやり抜いた実績だ。
学歴を比べてみよう。
| 候補者 | 所属 | 年齢 | 学歴 |
|---|
| 仲れいこ | 再生の道 | 36歳 | 早稲田大学卒(通信制) |
| 渋谷のぶゆき | 自民党 | 56歳 | 拓殖大学政経学部卒、東海大学大学院修了 |
| 原のり子 | 共産党 | 59歳 | 法政大学社会学部卒 |
| 細谷しょうこ | 国民民主党 | 71歳 | 大阪芸術大学中退 |
早稲田大学卒という学歴は、通信制とはいえ十分誇れるものだし、何より「社会人として働きながら、学び直した」というストーリーが強い。
さらに、夜職経験を持ちながら政治に挑むという異色のバックグラウンドも、これまでの都議会にはいない視点を持っている証だ。
つまり、仲れいこさんは「泡沫候補」ではない。社会経験と学び直しの実績を持つ、挑戦者としての資格がある人だ。
このことをもっと前面に出すべきだと思う。
投票率を上げることが、勝利の鍵
ここで重要な話をしたい。
仲れいこさんが勝つためには、投票率を上げるしかない。
前回(2021年)の北多摩第四選挙区の投票率は**40.29%だった。
でも、その前の2017年の投票率は51.66%**だったんだ。
つまり、投票率は10%以上下がっている。
「政治に関心がない」「誰に入れても同じ」という無関心層が、確実に増えている証拠だ。
じゃあ逆に考えよう。
投票率を10%上げることができれば、どうなるのか?
有権者数は約16万人。
投票率が40%から50%に戻れば、投票者は約64,000人 → 約80,000人に増える。
つまり、約16,000人の新しい票が生まれる可能性があるということだ。
ここで、再生の道の支持率(推定2%)が活きてくる。
2%の支持率がそのまま新たな16,000票に適用されれば、+3,200票が上積みされる計算になる。
さらに、無関心層の「今まで投票してこなかった層」は、既存の組織票よりも新しい挑戦者に票を入れやすい傾向がある。
だからこそ、投票率を上げる運動そのものが、仲さんの勝利に直結する。
投票率を上げるために必要なこと
では、投票率をどう上げるのか?
それは、ただ「投票に行こう」と言うだけでは足りない。
「なぜ今、投票が必要なのか」を伝えるメッセージが必要だ。
その鍵になるのが、**「小池都政のデメリット」と「二元代表制の機能不全」**だ。
- 北多摩地域は、都心部に比べて投資が後回しにされがちだ。
- 都議会は小池都政の言いなりになりすぎて、地域の声を届ける役割を果たしていない。
- 今のままでは、私たちの暮らしが良くなるとは思えない。
だから、こう訴えるべきだ。
「このままの小池都政に任せてはいけない。」
「今の都議会は、知事にNOと言えない議会だ。」
「地域の声を都政に届けるためには、再生の道の仲れいこさんのような人が必要だ。」
これを、街頭で、SNSで、ブログで、動画で、繰り返し繰り返し伝えていくしかない。
石丸さんは助けてくれない。
再生の道の代表である石丸さんは、正直、こういう地道な選挙戦術の先頭に立つ人ではないだろう。
彼は「自分たちでやれ」というスタンスで、仲れいこさんにも接すると思う。
だから、仲さん自身が、再生の道のメンバー自身が、投票率を上げるための活動をやるしかない。
- 「投票所に行こう」キャンペーンをやろう。
- 「今の都議会を変えよう」動画を撮ろう。
- 駅前で「あなたは投票に行きますか?」とシールアンケートをしよう。
- 北多摩の未来は、私たち一人ひとりの手にかかっているんだと伝えよう。
仲れいこさん、がんばって!
最後にもう一度言いたい。
仲れいこさん、僕はあなたの挑戦を応援しています。
「再生の道」という名前の通り、政治を再生するためには、新しい人が議会に入るしかない。
そして、その「新しい人」にふさわしいのが、仲れいこさんだと思っています。
だから、どうか最後まであきらめずに、戦い抜いてください。
投票率を上げて、無関心層を巻き込み、北多摩から東京を変えていってください。
がんばれ、仲れいこさん!